【獣医師監修】犬も「虫歯(う蝕)」になる?見分け方は?原因や症状、対処、治療法(費用)予防対策は?
犬は虫歯(う蝕)にはなりにくいものの、まったくならないというわけではなく、稀(まれ)に虫歯になる犬もいます。口を開けたら「歯に穴が開いていた」「歯が黒い、または茶色くなっていた」という時には動物病院で診てもらいましょう。そうならないためには、歯磨きとこまめな口の中のチェックが一番の予防です!
投稿日: 更新日:

日本獣医畜産大学(現:日本獣医生命科学大学)大学院 獣医学研究科 修士課程 修了。
1988年に埼玉県上尾市でフジタ動物病院を開院する。
同病院の院長として、獣医師15名、AHT・トリマー・受付31名、総勢46名のスタッフとともに活躍している。
【資格】
◇獣医師
【所属】
◆日本小動物歯科研究会 会長
◆公益社団法人 日本獣医学会 評議員
◆財団法人 動物臨床医学会 理事
◆公益財団法人 動物臨床医学研究所 評議員
◆日本獣医療倫理研究会(JAMLAS) 理事
◆NPO法人 高齢者のペット飼育支援獣医師ネットワーク 理事
◆日本獣医臨床病理学会 評議員
◆社団法人 日本動物病院福祉協会
◆世界動物病院協会
◆日本動物病院会
◆小動物臨床研究会さくら会
◆PCM 研究会
その他の会に所属し、研究活動を精力的に行っている。
◇岩手大学 農学部獣医学科 非常勤講師(2008~2012年)
◇帝京科学大学 生命環境学部 アニマルサイエンス学科 非常勤講師(2012年~)
◇日本大学 生物資源科学部 獣医学科 高度臨床獣医学 非常勤講師(2013年~)
【編著】
「基礎から学ぶ小動物の歯科診療 Vol.1」interzoo
「基礎から学ぶ小動物の歯科診療 Vol.2」interzoo
目次
犬の虫歯(う蝕)【原因・理由は?】

wassiliy-architect/ Shutterstock.com
犬の虫歯の原因
犬の虫歯は専門的に「う蝕」と言いますが、口内環境と細菌、食べ物、歯の形・質、デンタルケアの頻度などの悪条件が重なった時に発生しやすくなります。
犬の虫歯の発生は小さな細菌と、食べ物に含まれる糖質との関係から始まります。
口の中にいる細菌(主にミュータンス菌)は、歯に付いた食べかすに含まれる糖を分解し、歯垢(プラーク)を形成して歯に付着。
増殖していくうちにバイオフィルムと呼ばれる膜(まく)で自らを覆(おお)いはじめます。
さらに増殖が続くと、細菌は食べかすに含まれる糖を発酵させて酸を作り出し、歯の表面を酸性にしますが、この酸の濃度が高まるにつれて歯のミネラルが奪われ、エナメル質が溶け出してしまいます(脱灰)。
本来、多少エナメル質が溶けても唾液の作用により歯を作り直すことができるのですが(再石灰化)、酸濃度が高くなるとそれが追い付かず、やがて歯が破壊され、「虫歯」となってしまうのです。
【参照元】
・Hale, Fraser A.「Dental caries in the dog.」(The Canadian veterinary journal = La revue veterinaire canadienne vol. 50,12 [2009]: 1301-4.)
・Veterinary Practice「Dental caries lesions in dogs」
・Veterinary Practice News「Do Dogs and Cats Get Cavities?」
・dvm360「Detection, treatment of dental caries in dogs」
・PETMD「Cavities in Dogs」
犬が虫歯になりにくい理由は?

mraoraor / PIXTA(ピクスタ)
実は、「犬は虫歯にはなりにくい」と言われています。
その理由として考えられるのは以下の3つ。
犬が虫歯になりにくい【理由】
✓犬の口の中はpH8~9の弱アルカリ性であること
✓唾液(だえき)成分に含まれるアミラーゼが非常に少ないこと(アミラーゼはデンプンを糖に分解する時に必要な酵素)
✓歯が尖った形状をしており、歯の表面に虫歯菌が付着しにくいこと
しかし、稀(まれ)に虫歯になる犬もおり、カナダでの獣医歯科記録の分析では、その割合は5.3%との報告があります。
Hale FA.「Dental caries in the dog.」(J Vet Dent. 1998 Jun;15(2):79-83.)
犬の虫歯(う蝕)【症状(初期)・兆候】

damedeeso / PIXTA(ピクスタ)
犬の虫歯の症状①【歯】
犬の虫歯では、次のような症状が見られます。
犬の虫歯【症状】
✓歯の色が濁(にご)って見える、ザラザラとしてつやがない
✓歯に黒い、または茶色い部分がある
✓歯に穴が開いている、歯が欠けている
✓進行するほどに歯が大きく破壊され、歯の中が見えている
✓口臭がある
犬の虫歯の症状②【犬の様子】

mon / PIXTA(ピクスタ)
「象牙質(ぞうげしつ)」や「歯髄(しずい)」まで虫歯菌が侵食し、痛みが出てくると犬の様子にも変化が見られます。
犬の虫歯【犬の様子】
✓口を触ろうとすると嫌がる
✓足で口を触ろうとする、口を何かにこすりつけるなど口を気にする素振りが見られる
✓ご飯がうまく食べられない
✓食べたり、物をかじったりしている途中で妙な声を出す
✓ご飯を食べようとしない
犬の虫歯(う蝕)【なりやすい犬種】

StudioCAXAP/ Shutterstock.com
虫歯はどんな犬でもなる可能性はありますが、特に以下のような犬はリスクが高いと言えるでしょう。
甘い物、発酵性炭水化物をよく口にする犬
糖の中でも、「スクロース(ショ糖/砂糖)」はもっとも虫歯になりやすい糖とされます。
また、発酵を起こす炭水化物(糖質)のことを発酵性炭水化物(発酵性糖質)と言い、多くの炭水化物がそれにあたりますが、細菌が糖を代謝して酸を作り出す際のエサになります。
【発酵性炭水化物の例】
| 【糖】 | 【食べ物】 |
|---|---|
| ブドウ糖 | 米、パン、果物、いも類 |
| 果糖 | 果物、はちみつ、ジュース類 |
| ショ糖 | 砂糖、はちみつ、果物 |
| 乳糖 | 牛乳 |
| 麦芽糖 | 麦芽、甘酒、さつまいも |

sdominick / iStock
口の中が乾きやすい、唾液分泌量が少ない犬
犬の唾液(だえき)には殺菌作用や歯の再石灰化、酸性度・アルカリ度を一定に保つ、口腔粘膜の保護などの働きがあり、唾液の分泌量が少ないと虫歯になりやすいと言われます。
歯石が付着している犬
歯石があることで虫歯菌(主にミュータンス菌)が繁殖しやすい環境になっています。
歯並びの悪い犬
歯並びが悪いと歯垢・歯石が付きやすくなります。
歯磨き、デンタルケアをしていない犬
歯の手入れをしないと歯垢・歯石が増えやすくなってしまいます。
【参照元】厚生労働省e-ヘルスネット「う蝕の原因とならない代用甘味料の利用法」
犬の虫歯(う蝕)【検査・治療法は?】

Ivonne Wierink/ Shutterstock.com
犬の虫歯(う蝕)【検査】
犬の虫歯では、主に次のような検査が行われます。
犬の虫歯検査①【視診による患部の確認】
エキスプローラー(探針)という歯科用器具を用いて手に伝わる感触から、犬のエナメル質や象牙質がどの程度破壊されているか、歯髄(しずい)が露出しているかなど、虫歯の侵食具合を調べます。
併せて、歯石が認められれば、その付着具合を確認する他、歯周プローブという器具では歯周ポケットの深さを測り、必要に応じて歯垢染色液による検査や歯垢・歯石検査用ライトによる検査などを行ないます。
犬の虫歯検査②【レントゲン検査】

FatCamera / iStock
歯科用レントゲン写真を撮ることで、犬の歯髄(しずい)への侵食があるかも含め、視覚的に病態を確認します。
犬の虫歯検査③【CT検査】
犬の鼻腔内(びくうない)の炎症も疑われる時などは、CT検査が行われることもあります。
犬の虫歯(う蝕)【治療】

HIME&HINA / PIXTA(ピクスタ)
犬の虫歯の治療は患部の状態によって若干違いが生じます。
犬の虫歯治療①【軽度の場合】
犬のエナメル質に小さな穴が開いている程度、象牙質(ぞうげしつ)もそれほど侵食されていないなど虫歯の侵食が初期で軽度な場合は、病変部分を削り取り、コンポレットレジン(CR)という歯科用の充填材(じゅうてんざい)を用いて歯の形を修復しますが、仕上げにフッ化物を塗布することもあります。
コンポレットレジンは人間の歯科治療でもよく使用されており、白い修復材で、ペースト状の形質ながら光をあてると固まるという特質があり、虫歯や欠けた歯などの接着修復に用いられています。
見た目は綺麗に仕上がり、比較的耐久性や強度に優れますが歯石が付着しやすくもあります。
犬の虫歯治療②【中度の場合】

phichat / PIXTA(ピクスタ)
犬の虫歯の侵食が「歯髄(しずい)」にまで及んでいる場合は、細菌感染を抑えるために歯内治療(根管治療)が必要となり、その後に歯の修復を行ないます。
軽度の虫歯の場合も含め、治療後は「3ヶ月後」「半年後」「1年後」など定期的に治療した歯の状態を確認することが大切です。
犬の虫歯治療③【重度の場合】
犬の歯冠が大きく破壊されている、歯の根尖(根元)まで炎症が重度に及んでいるなどの場合や根尖周囲まで炎症が進んでいる場合は、抜歯が適用されます。
犬の虫歯(う蝕)【治療費(手術費用)・治療薬】

Igor Chus/ Shutterstock.com
犬の虫歯が進行していた場合は、状況に応じ、抗生物質や抗菌剤などの抗菌薬が処方されます。
【歯石除去に関連する治療費の目安】
| 【項目】 | 【平均的料金】 |
|---|---|
| 歯石除去 | ~1万2,500円 |
| 抜歯 | ~5,000円 |
| 歯内治療(根管治療) | ~1万2,500円 |
| レントゲン検査/単純撮影 | ~7,500円 |
| CT検査/造影なし 〃 /造影あり | ~4万円 5万円以上~ |
| 麻酔/局所麻酔 〃 /全身麻酔 | ~5,000円 ~1万5,000円 |
| 血液検査/採血料 〃 /CBC検査 〃 /生化学検査 | ~2,000円 ~3,000円 ~7,500円 |
| 調剤料(内用/1回あたり) | ~1,000円 |
公益社団法人 日本獣医師会「家庭飼育動物(犬・猫)の診療料金実態調査及び飼育者意識調査 調査結果(平成27年6月)」を参考に作成
犬の虫歯(う蝕)【ペット保険の適用は?】

YAKOBCHUK VIACHESLAV/ Shutterstock.com
ペット保険では歯科治療全般が補償対象外になっているもの、歯周病は対象となるものなど各社各様です。
一般的に、予防にあたるものは補償対象外となり、歯石除去のような処置もそれに含まれます。
ただし、「全身麻酔をして行なう処置は手術にあたり、補償対象となる」「他の歯科疾患があり、その治療の一環として行なう歯石除去や抜歯は補償対象となる」など、ペット保険会社によって細かく条件が設けられていることがあるので、詳しくは加入しているペット保険会社に問い合わせてみてください。
これからペット保険の加入を考えている場合には、愛犬の健康リスクと併せ、各保険プランの条件をよく比較検討してから選ぶことをおすすめします。
犬の虫歯(う蝕)【食事・予防対策は?】

LightField Studios/ Shutterstock.com
次のようなことは、愛犬の虫歯予防につながるでしょう。
犬の虫歯の予防対策①【定期的な歯磨き】
犬の場合、歯垢が歯石に変化するのは3~5日程度なので、少なくとも1日おきに歯磨きをするのが理想的
犬の虫歯の予防対策②【口の中をチェックする習慣】
虫歯になりやすいのは上顎(うわあご)の第1後臼歯および第2後臼歯、それと噛み合わさる下顎(したあご)の後臼歯、いずれにしても奥歯が多い。
歯のチェックをする時は、歯のくぼみや奥歯までしっかりと確認を。
また、前出のカナダの報告では、虫歯は左右対称の歯に起こることが多いとのことなので、気になる歯があった時には反対側の歯もチェックをしましょう。
犬の虫歯の予防対策③【歯垢・歯石の予防、除去作用のデンタルケアグッズを併用】

たけぽん / PIXTA(ピクスタ)
物をかじることで、犬の唾液の分泌を促すことができる他、歯垢を落とす効果も期待できるが、硬過ぎる物は破折(歯が折れること)を起こすことがあるので注意。
犬の虫歯の予防対策【サプリメントを与える】
乳酸菌生産物質には歯周病菌の抑制効果があると考えられており、乳酸菌を含む食品やサプリメントなどを与えてみるのも良い。
なお、バナナのような糖度と粘度の高い物を食べた後は虫歯菌が活動しやすくなるので、歯磨きをする、与える回数を少なくするなど配慮をするようにしましょう。
小野田繁「乳酸菌生産物質とは何か? またその歯科応用について」(日本歯科東洋医学会誌 Vol.26, No.1・2 2007年 1-9)
子犬・老犬の虫歯(う蝕)【注意点・ケア方法は?】

cynoclub / PIXTA(ピクスタ)
犬の虫歯の注意点・ケア方法①【子犬】
犬の歯並びは歯石ができやすいかどうかにも関係するので、特に歯の生え変わりの時期には、以下のようなことをチェックしておきましょう。
犬の歯の本数(乳歯は28本、永久歯は42本)
乳歯が残っていないか
犬の歯の生え方はどうか(生える向きや傾きなど)
犬の歯の形はどうか(でこぼこや傷、穴などないか)
犬の虫歯の注意点・ケア方法②【老犬(高齢犬)】

kei.channel / PIXTA(ピクスタ)
歯に歯石が付いていることが多く、虫歯になるリスクが高いと言えるのが老犬。
物をかじって遊ぶことも少なくなり、水を飲む意識も低下しがちなことから、口の中が乾きやすい傾向にもあります。
現在では老犬に合った麻酔方法もあり、犬の状況によっては老犬でも麻酔下での歯石除去ができる場合もあるので、気になる時には動物病院で相談してみてください。
また、十分な水分が摂れるよう、食事の水分量を増やす、水飲み場を複数用意するなど配慮してあげたいものです。
犬の虫歯(う蝕)【間違いやすい病気は?】

Kzenon/ Shutterstock.com
虫歯と間違いやすい病気①【エナメル質形成不全】
犬の「エナメル質形成不全」とは、エナメル質の形成が不十分で、歯の表面(エナメル質)がところどころ欠け、でこぼこになる、歯に穴が開いている、歯が黄褐色~茶色に変色する、知覚過敏がある(象牙質が露出した場合)などの症状が見られる歯科疾患です。
生後1ヶ月~4ヶ月の頃にウイルス性疾患(特にジステンパー)や発熱性疾患、重度の消化器障害、栄養障害、外傷などにさらされるとこの病気を発症することが多いと言われています。
虫歯と間違いやすい病気②【外傷】
怪我や犬同士のケンカなどにより歯が折れたり、破壊されたりすることもあります。
犬の虫歯(う蝕)【まとめ】

mrwed54 / PIXTA(ピクスタ)
犬が虫歯になることがあるすれば、要チェックなのは歯の形がくぼんでいる部分、そして奥歯。
こまめに愛犬の口の中をチェックしている飼い主さんでも、実は奥歯まではあまりよく見ていないということが意外にあるのではないでしょうか。
愛犬の健康のため、歯磨きと、奥歯までの口腔内チェックで虫歯を予防しましょう。
【併せて読まれている歯科・病気関連の記事】
↓ ↓ ↓
みんなのコメント
編集部のおすすめ記事
- 【獣医師監修】犬が餅(もち)を食べても大丈夫?のどに詰まらせると窒息死も!対処法や予防対策は?
- 正月になると食べる機会の増える、餅(もち)。焼き餅や雑煮、きな粉餅などを、愛犬にも食べさせてあげたいと思う人もいるでしょう。犬に餅を食...
- 【獣医師監修】犬がかまぼこ(板)を食べても大丈夫?塩分や添加剤は問題ない?適量や栄養、注意点!
- 白身魚のすり身を練った、かまぼこ(蒲鉾)。人間用では、おせち料理やうどん、蕎麦、茶碗蒸しの具としてもよく使われますよね。魚のすり身とい...
- 【獣医師監修】犬の歯髄炎(しずいえん)原因や症状は?対処・治療法(抜歯)、治療費、予防対策!
- 犬の歯髄炎とは、多くは歯が破折し歯の中心部にある歯髄に細菌が入り込み、炎症が起きた状態です。歯が折れたり、擦り減り歯髄が露(あらわ)に...
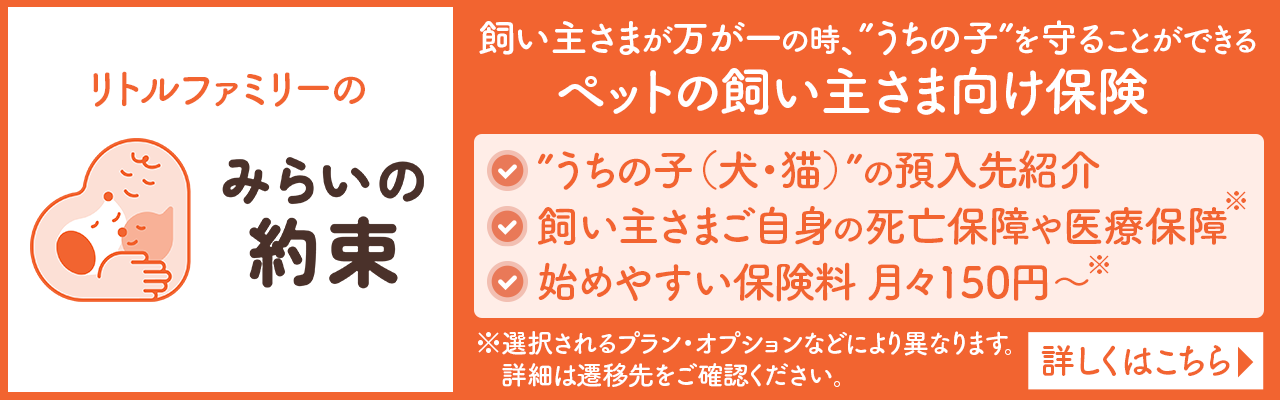










あなたも一言どうぞ
コメントする