【獣医師監修】犬の「根尖周囲病巣」原因や症状は?対処・治療法、治療(手術)費、予防対策は?
犬の根尖周囲病巣(こんせんしゅういびょうそう)とは、外からは見えない歯の根元の周囲組織に炎症が起こった状態を言い、肉芽腫や嚢胞(のうほう)、膿瘍(のうよう)などの病変が生じます。原因は歯周病や破折(はせつ)、う蝕(うしょく/虫歯のこと)など。抜歯や歯内治療(根管治療)などの歯科治療が必要になります。
投稿日: 更新日:

日本獣医畜産大学(現:日本獣医生命科学大学)大学院 獣医学研究科 修士課程 修了。
1988年に埼玉県上尾市でフジタ動物病院を開院する。
同病院の院長として、獣医師15名、AHT・トリマー・受付31名、総勢46名のスタッフとともに活躍している。
【資格】
◇獣医師
【所属】
◆日本小動物歯科研究会 会長
◆公益社団法人 日本獣医学会 評議員
◆財団法人 動物臨床医学会 理事
◆公益財団法人 動物臨床医学研究所 評議員
◆日本獣医療倫理研究会(JAMLAS) 理事
◆NPO法人 高齢者のペット飼育支援獣医師ネットワーク 理事
◆日本獣医臨床病理学会 評議員
◆社団法人 日本動物病院福祉協会
◆世界動物病院協会
◆日本動物病院会
◆小動物臨床研究会さくら会
◆PCM 研究会
その他の会に所属し、研究活動を精力的に行っている。
◇岩手大学 農学部獣医学科 非常勤講師(2008~2012年)
◇帝京科学大学 生命環境学部 アニマルサイエンス学科 非常勤講師(2012年~)
◇日本大学 生物資源科学部 獣医学科 高度臨床獣医学 非常勤講師(2013年~)
【編著】
「基礎から学ぶ小動物の歯科診療 Vol.1」interzoo
「基礎から学ぶ小動物の歯科診療 Vol.2」interzoo
目次
- 犬の根尖周囲病巣(こんせんしゅういびょうそう)【原因は?】
- 犬の根尖周囲病巣(こんせんしゅういびょうそう)【症状】
- 犬の根尖周囲病巣(こんせんしゅういびょうそう)【なりやすい犬種】
- 犬の根尖周囲病巣(こんせんしゅういびょうそう)【診断・治療法は?】
- 犬の根尖周囲病巣(こんせんしゅういびょうそう)【治療薬・治療費(手術費用)】
- 犬の根尖周囲病巣(こんせんしゅういびょうそう)【食事・予防対策は?】
- 高齢犬(老犬)の根尖周囲病巣(こんせんしゅういびょうそう)【注意点・ケア方法は?】
- 犬の根尖周囲病巣(こんせんしゅういびょうそう)【間違いやすい病気は?】
- 犬の根尖周囲病巣(こんせんしゅういびょうそう)【まとめ】
犬の根尖周囲病巣(こんせんしゅういびょうそう)【原因は?】

犬の歯のつくりと組織。「根尖(こんせん)」とは、歯の根っこの先端部分(赤丸部位)を指す。根尖周囲病巣は、この根尖の周囲にある組織に炎症が生じる。
犬の歯の「根尖(こんせん)」とは歯の根っこの先端および周辺を指し、イラストの赤丸部分にあたります。
犬の根尖周囲病巣(こんせんしゅういびょうそう)は、この根尖の周囲に炎症が起こった状態を言い、状況により、肉芽腫(にくがしゅ/ぽつぽつとした隆起)や嚢胞(のうほう/液体の分泌物が袋状に溜まったもの)、膿瘍(のうよう/膿が溜まった状態)などが生じますが、それぞれ根尖膿瘍(こんせんのうよう)、歯根嚢胞(しこんのうほう)などと呼ばれることもあります。
主な原因として考えられるものは、以下の通りです。
犬の根尖周囲病巣の原因①【破折(はせつ)・咬耗(こうもう)】
犬の「破折」とは歯が折れることを言い、咬耗は物を長時間かじり続けることで歯が擦り減った状態を言います。
破折や咬耗により、歯髄(しずい)が露出(露髄/ろずい)した場合、そこから細菌感染を起こし、進行すると根尖周囲病巣につながることがあります。
犬の根尖周囲病巣の原因②【歯周病】

iStock.com/IgorChus
犬の「歯周病」は歯垢(プラーク)に含まれる細菌が歯周組織に入り込むことで炎症を引き起こす歯科疾患ですが、進行するにつれ、炎症が根尖部にまで広がると、根尖部周辺の歯周組織(歯根膜・歯槽骨・歯肉・セメント質の4つで構成される)が破壊され、硬い歯槽骨も吸収されて(溶けて)しまいます。
つまり、根尖周囲病巣を呈するわけです。
犬の根尖周囲病巣の原因③【う蝕(うしょく/虫歯)】
犬のう蝕とは虫歯のことで、犬では稀(まれ)です。
歯周病同様、進行すれば根尖部を破壊してしまいます。
犬の根尖周囲病巣の原因④【変形歯】
犬の「変形歯」とは多根歯における歯の形態異常で、歯根の分岐部(根分岐部)に副根管が存在して歯根膜と歯髄(しずい)がつながり、レントゲン検査上、歯根同士が近づいて見えることを特徴とします。
歯髄に隣接する副根管(ふくこんかん)に細菌が侵入して歯髄炎(しずいえん)を起こし、進行して歯髄壊死(しずいえし)となり、根尖周囲病巣につながることがあります。
【参照元】
渡邊一弘 他「過剰根を伴う上顎第4 前臼歯の根尖周囲病巣による内歯瘻の犬の1例」(日獣会誌67, 340-344 [2014])
犬の根尖周囲病巣(こんせんしゅういびょうそう)【症状】

iStock.com/nemoris
犬の根尖周囲病巣では、主に次のような症状が見られます。
犬の根尖周囲病巣【主な症状】
| 【原因】 | 【原因別の症状や病態】 |
|---|---|
| 破折・咬耗 | ・歯が折れている、欠けている、割れている ・歯が擦り減っている ・歯髄が露出している(露髄) |
| 歯周病 | ・歯垢、歯石が付着している ・口臭が強い ・歯肉から出血がある |
| う蝕 (虫歯) | ・口臭が強い ・虫食いのような穴が開いている ・上下の歯が噛み合わさる面が欠損している |
| 変形歯 | ・(見た目ではわかりにくい) |
| 【主な症状】 |
|---|
| ・歯肉(歯茎)が赤く腫れている ・歯がグラグラしている ・上顎や下顎など顔が腫れている ・口の周りを気にする(こすりつける、足で触ろうとするなど) ・口の周りに触られるのを嫌がる ・歯磨きを嫌がる ・ごはんを口からこぼす ・食べている最中、妙な声を出す ・ごはんを食べたがらない ・歯の形態が普通でない |
犬の根尖周囲病巣が進行すると、細菌の増殖によって口腔粘膜に穴が開いてしまう内歯瘻(ないしろう)をはじめ、目の下や顎の下などに穴が開く外歯瘻(がいしろう)、口腔と鼻腔とを隔てる骨が溶けて両者がつながってしまう口腔鼻腔瘻(こうくうびくうろう)、骨が溶けることによる下顎骨骨折(かがくこつこっせつ)などを引き起こすことがあるので、注意が必要です。
犬の根尖周囲病巣(こんせんしゅういびょうそう)【なりやすい犬種】

iStock.com/cunfek
根尖周囲病巣はどんな犬でも発症する可能性はありますが、特に以下のような犬は発症リスクが高い傾向にあるため、注意してあげたほうがいいでしょう。
なりやすい犬種①【破折が原因の場合】
噛む力が強い中型犬・大型犬
なりやすい犬種②【歯周病が原因の場合】
トイ・プードル
ミニチュア・ダックスフンド
ヨークシャー・テリア などの小型犬
なりやすい犬種③【変形歯が原因の場合】
小型犬
下顎(したあご)のもっとも大きな両側の奥歯(第1後臼歯)に多く発症する傾向があります。
犬の根尖周囲病巣(こんせんしゅういびょうそう)【診断・治療法は?】
診断

Henk Vrieselaar/ Shutterstock.com
炎症を起こしている根尖部の状態を確認し、診断としての評価をするためには「歯科レントゲン検査」が有効です。
愛犬に歯周病がある場合には、エキスプローラーという歯科用器具で歯垢・歯石の付き具合をチェックする、同じく歯周プローブという器具では歯周ポケットの深さを測り、歯と歯肉の密着度の喪失程度(アタッチメントロス)を診るなどします。
その他、炎症範囲が広いと思われる時などはCT検査が行われることもあります。
治療

iStock.com/Savany
それぞれの原因に沿った治療を行いますが、多くの場合、抜歯が必要となり、破折などには炎症が軽度の場合に限っては歯内治療(根管治療)が施されることもあります。
治療①【破折・咬耗が原因の場合】
「破折・咬耗」が原因の場合、炎症が軽度であれば、歯髄の全部を抜いて根管に充填材(詰め物)をした後に歯冠修復するといった歯内治療(根管治療)がなされることもあります。
治療②【歯周病が原因の場合】
「歯周病」が原因の場合、すでに歯槽骨が溶け、炎症が重度であることが多く、抜歯が適用されるケースがほとんどとなります。
治療③【う蝕(虫歯)が原因の場合】
「う蝕(虫歯)」が原因の場合、炎症が軽度であれば、う蝕した歯の治療(歯内治療や歯冠修復)を行いますが、重度であると抜歯の対象になります。
治療④【変形歯が原因の場合】
変形歯が原因の場合は、抜歯が必要です。
その際、両側の同じ歯が障害を起こしていることが多いため、両側とも抜歯をします。
【参照元】
フジタ動物病院「歯科の治療例/歯内治療(抜髄根管充填)について」歯科の治療例 - 埼玉・上尾で動物病院をお探しの方へ【フジタ動物病院】
犬の根尖周囲病巣(こんせんしゅういびょうそう)【治療薬・治療費(手術費用)】

Studio Pet Photos/ Shutterstock.com
状況に応じて抗生物質や抗菌薬、鎮静剤などの薬が処方されるでしょう。
【根尖周囲病巣に関連する治療費の目安】
| 【項目】 | 【平均的料金】 |
|---|---|
| 抜歯 | ~5,000円 |
| 歯内治療(根管治療) | ~1万2,500円 |
| レントゲン検査/単純撮影 | ~7,500円 |
| CT検査/造影あり 〃 /造影なし | ~5万円以上 ~4万円 |
| 麻酔/局所麻酔 〃/全身麻酔 | ~5,000円 ~1万5,000円 |
| 調剤料(内用/1回あたり) | ~1,000円 |
| 処方箋 | ~2,000円 |
【参照元】
公益社団法人 日本獣医師会「家庭飼育動物(犬・猫)の診療料金実態調査(平成27年度)」
犬の根尖周囲病巣(こんせんしゅういびょうそう)【食事・予防対策は?】
食事

iStock.com/smrm1977
犬の根尖周囲病巣では重度になるにつれ、かなり痛みがありますので、歯がぐらついている場合などは硬い物は避け、柔らかく、飲み込みやすい食事を与えてあげるといいでしょう。
場合によっては、流動食のようなタイプもいいのではないでしょうか。
しかし、早めに治療することが大切です。
予防法

iStock.com/lilu13
次のようなことは愛犬の根尖周囲病巣の予防につながるでしょう。
予防法①【破折や咬耗の予防のため】
硬過ぎる物はかじらせない(例:ひづめ、ガム、骨、おもちゃ、石、ケージ)
長時間、同じ物をかじらせない
予防法②【歯周病予防のため】
定期的に歯磨きをする
歯垢・歯石は早めに除去する
予防法③【病気の早期発見のため】
普段のお手入れのついでに口の中もチェックする
高齢犬(老犬)の根尖周囲病巣(こんせんしゅういびょうそう)【注意点・ケア方法は?】

iStock.com/smilingsunray
老犬は歯周病のリスクが高く、成犬時の歯周病が進行して、高齢になってから根尖周囲病巣を発症することも珍しくありません。
ですから、歯垢・歯石は放置せずに、できるだけ若いうちに除去しておくことをお勧めします。
老犬になるといかにQOL(生活の質)を高め、その犬なりの健康を維持してあげられるかがより大切になってきます。
そのためには、歯の痛みに耐える日々を送らせるのではなく、思い切って抜歯を考えるのも一つの選択肢になることがあるでしょう。
もちろん、老犬には麻酔のリスクがつきまといますが、事前に体の状態を十分に検査して大きな異常がなければ、犬の状況によっては老犬でも抜歯ができるケースも少なくないので、必要な場合には動物病院で相談してみてください。
犬の根尖周囲病巣(こんせんしゅういびょうそう)【間違いやすい病気は?】

trinityfoto/ Shutterstock.com
犬の根尖周囲病巣は埋伏歯(まいふくし)により形成された嚢胞(含歯性嚢胞/がんしせいのうほう)などとの識別が必要です。
犬の埋伏歯とは永久歯が生えてこれずに顎(あご)の中に埋もれたままの状態を言い、時間が経つにつれ、埋伏歯の周囲に嚢胞ができてしまうことがあります。
犬の根尖周囲病巣(こんせんしゅういびょうそう)【まとめ】

Milosz Aniol/ Shutterstock.com
犬の歯は歯髄が感染を受けて歯髄炎となると強い痛みが出ると言われます。
それが歯の根元まで感染となると、人間ほどには痛みを外に表さない犬であってもたいへん辛いことでしょう。
「元気がない」「うずくまって動きたがらない」「好きだったことも喜ばない」「表情が乏しくなった」「怒りっぽくなった(時に噛もうとする)」「口を触られるのを嫌がる」などは犬が痛みを感じている時に出すサインでもあります。
そのような様子が見られた時には、歯や口の中も含め、どこか異常はないかチェックしてみるといいでしょう。
【併せて読まれている病気・医療関連の記事】
↓ ↓ ↓
みんなのコメント
編集部のおすすめ記事
- 【獣医師監修】犬が餅(もち)を食べても大丈夫?のどに詰まらせると窒息死も!対処法や予防対策は?
- 正月になると食べる機会の増える、餅(もち)。焼き餅や雑煮、きな粉餅などを、愛犬にも食べさせてあげたいと思う人もいるでしょう。犬に餅を食...
- 【獣医師監修】犬がかまぼこ(板)を食べても大丈夫?塩分や添加剤は問題ない?適量や栄養、注意点!
- 白身魚のすり身を練った、かまぼこ(蒲鉾)。人間用では、おせち料理やうどん、蕎麦、茶碗蒸しの具としてもよく使われますよね。魚のすり身とい...
- 【獣医師監修】犬の歯髄炎(しずいえん)原因や症状は?対処・治療法(抜歯)、治療費、予防対策!
- 犬の歯髄炎とは、多くは歯が破折し歯の中心部にある歯髄に細菌が入り込み、炎症が起きた状態です。歯が折れたり、擦り減り歯髄が露(あらわ)に...
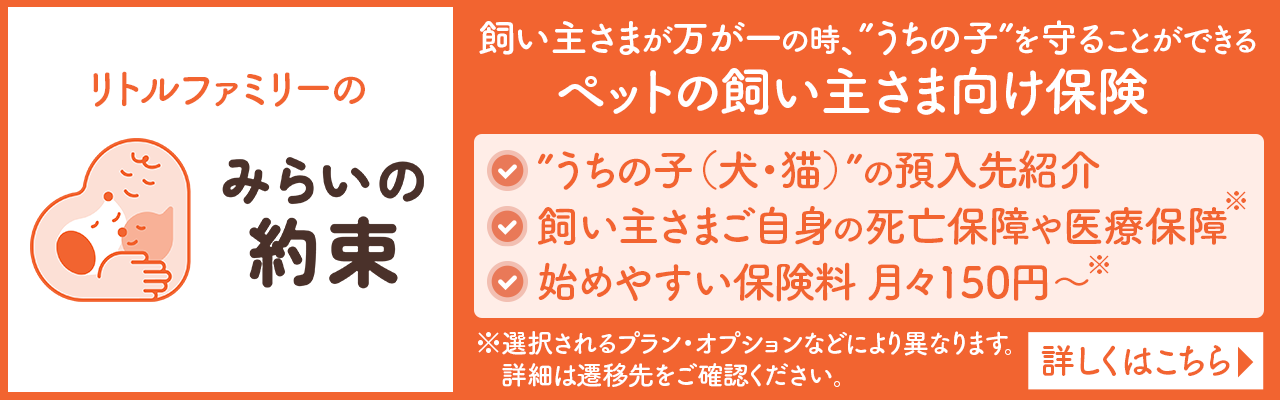









あなたも一言どうぞ
コメントする